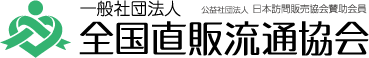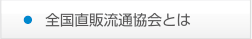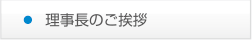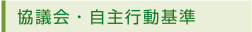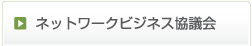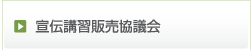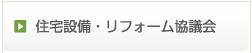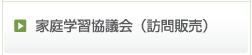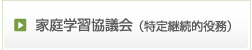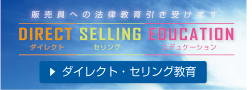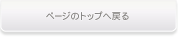主催:御殿場市役所 くらしの安全課
中西載慶講師は若さを保つ食生活について、タンパク質やカルシウムを充分に摂るバランスのよい食生活、発酵食品を適切かつ継続的に摂取し腸内環境を整えることが重要であるとお話しいただきました。とくに、発酵食品の中でも納豆とヨーグルトはアンチエイジングにおすすめと紹介し、その歴史や有効性について解説しました。中西講師のお話は図表などを用いてとても分かりやすく、講座後も受講者から質問を受けるなど盛況のうちに幕を閉じました。
ブログアーカイブ
「表示から考える食品の選び方について〜サプリメント〜」
主催:茂原市役所 市民部生活
冒頭、商品パッケージに表示された様々なマークについて説明しました。そのうえで、WHO(世界保健機関)が「健康」について、肉体面、精神面、社会的なつながりについて言及していることを解説。また、サプリメントで健康維持することで自分が一体何をしたいのかの目標を定めた上で摂取することが大切であることを強調しました。さらに、サプリメントについて誤解しやすいことを具体的な事例を挙げて注意喚起しました。かかりつけ医から出された薬剤を処方している場合の注意点として、まずかかりつけ医に相談した上で摂取を始めることが大切であることにも言及しました。
冒頭、商品パッケージに表示された様々なマークについて説明しました。そのうえで、WHO(世界保健機関)が「健康」について、肉体面、精神面、社会的なつながりについて言及していることを解説。また、サプリメントで健康維持することで自分が一体何をしたいのかの目標を定めた上で摂取することが大切であることを強調しました。さらに、サプリメントについて誤解しやすいことを具体的な事例を挙げて注意喚起しました。かかりつけ医から出された薬剤を処方している場合の注意点として、まずかかりつけ医に相談した上で摂取を始めることが大切であることにも言及しました。
「円満な相続実現のために」
主催:富士市 市民部市民安全課
皆さんは相続についてどんな「想い」をお持ちですか? 「私の家は親族ともめるほど財産がないから関係ないだろう」と他人事だと思ってはいませんでしょうか。 近年は財産が少ない家ほど遺産分割が思うようにいかないケースが増えており、遺産分割関連の審判や調停件数は右肩上がりに推移しています。相続トラブルを未然に防ぐ上で、相続を早く準備するに越したことはないと言えます。講座では円満な遺産分割を確実に実現する上で「い まできることは何か」「なぜ遺言書を作成することが大切なのか」など、相続を考える際に押さえておきたいポイントや対策を分かりやすく解説しました。
皆さんは相続についてどんな「想い」をお持ちですか? 「私の家は親族ともめるほど財産がないから関係ないだろう」と他人事だと思ってはいませんでしょうか。 近年は財産が少ない家ほど遺産分割が思うようにいかないケースが増えており、遺産分割関連の審判や調停件数は右肩上がりに推移しています。相続トラブルを未然に防ぐ上で、相続を早く準備するに越したことはないと言えます。講座では円満な遺産分割を確実に実現する上で「い まできることは何か」「なぜ遺言書を作成することが大切なのか」など、相続を考える際に押さえておきたいポイントや対策を分かりやすく解説しました。
「機能性表示食品について」
主催:福島市消費生活センター
機能性表示食品と言えば、最近、紅麹サプリですが、講師の今川氏はサプリメントは健康維持・増進に役立つもので、医薬品のような効果を期待するのではないが、自分にとって必要な成分を手軽に摂取することができる利点があるので、 食事量が減った高齢者には適したものである、 との説明もありました。最後に健康は目的ではなく、生活の質を維持・向上させるための手段である、との正しい認識をもって楽しく、元気に過ごしていただきたい、と締めくくりました。
機能性表示食品と言えば、最近、紅麹サプリですが、講師の今川氏はサプリメントは健康維持・増進に役立つもので、医薬品のような効果を期待するのではないが、自分にとって必要な成分を手軽に摂取することができる利点があるので、 食事量が減った高齢者には適したものである、 との説明もありました。最後に健康は目的ではなく、生活の質を維持・向上させるための手段である、との正しい認識をもって楽しく、元気に過ごしていただきたい、と締めくくりました。
「高齢者のためのスマホ活用術」
主催:新潟市消費生活センター
前回、米津講師で好評を博した同テーマを今回は大森講師が担当しました。最近では高齢者の方も多くがスマホを使われておりますが、SNS等の利用によ るトラブルも頻発しています。賢く安全に使うポイントをITインストラクターの米津講師が解説しました。まず、日ごろのスマホの利用目的の確認として、メール、電話、写真、ネットショッピング等、確認してみることから始まり、指紋認証やパスワード、ロック機能等のセキュリティーの状況、紛失した際の連絡先や契約内容の確認が大切と説きます。また、SMSを利用したフィシング詐欺の事例や大手通販サイトに似せたサイトに誘導する偽メール、SIMスワップ詐欺、ワンクリック詐欺、等の事例を通じて注意を促しました。 更に、日常で使える便利な機能や便利なアプリ、災害時に役立つ災害伝言ダイヤルについて紹介するなど、大変、内容の濃いものとなりました。
前回、米津講師で好評を博した同テーマを今回は大森講師が担当しました。最近では高齢者の方も多くがスマホを使われておりますが、SNS等の利用によ るトラブルも頻発しています。賢く安全に使うポイントをITインストラクターの米津講師が解説しました。まず、日ごろのスマホの利用目的の確認として、メール、電話、写真、ネットショッピング等、確認してみることから始まり、指紋認証やパスワード、ロック機能等のセキュリティーの状況、紛失した際の連絡先や契約内容の確認が大切と説きます。また、SMSを利用したフィシング詐欺の事例や大手通販サイトに似せたサイトに誘導する偽メール、SIMスワップ詐欺、ワンクリック詐欺、等の事例を通じて注意を促しました。 更に、日常で使える便利な機能や便利なアプリ、災害時に役立つ災害伝言ダイヤルについて紹介するなど、大変、内容の濃いものとなりました。